Designer's TALK
- 空間と素材
空間のつくり手が語る、空間と素材へのアプローチ
日本の伝統的な素材や技術をインテリアに活用
t.c.k.w 立川 裕大

さまざまなマテリアルサンプルが並ぶt.c.k.wのオフィスにて(特記以外の写真:深沢 次郎)
立川裕大さんはデザイナーではない。「伝統技術ディレクター」だ。
漆や鋳物、ブナコ、和紙、竹、箔、組子といった、日本の各地に息づく伝統的な素材や技術。
立川さんはそれらを用いて家具や照明器具、内装材などのインテリアエレメントを、建築家やデザイナーのフルオーダーにより製作する「ubushina(ウブシナ)」という事業を進めている。
商品ではなく「技術を売る」という発想の転換が、この事業の道を切り開いた。
伝統技術の維持・保存にとどまらず、新たな価値を生み出し、ものづくりの領域を広げている点が画期的だ。
― 立川さんが2005年に始めた「ubushina」事業では、各地の職人やメーカーと、建築家やデザイナーの間を取り持ち、製作プロセス全般をマネージメントしながら、伝統技術を用いたインテリアエレメントのオーダーメイドに対応しています。現在、どれくらいの数の職人やメーカーと連携しているのですか?
立川:大小合わせて300くらいでしょうか。それでもほんの一部です。日本には経済産業省が指定するだけで230品目の伝統的工芸品があります(2017年12月時点)。それらに従事する事業者の数は、インディペンデントの職人を含めると把握できないくらいと言っていいでしょう。この多様さは日本の絶対的な強みです。
― オフィスに並ぶたくさんのマテリアルサンプルを見ていると、楽しくなりますね。建築家やデザイナーは創造力が大いに刺激されることでしょう。

立川 裕大 Yudai Tachikawa
1965年長崎県生まれ。大学卒業後、カッシーナジャパン、インテリアセレクトショップを経て、1999年t.c.k.wを設立。「ubushina」の活動により2016年、伝統工芸の世界で革新的な試みを行う個人団体に贈られる三井ゴールデン匠賞を受賞



立川:日本にはまだかろうじて伝統技術が残っています。以前、プロジェクトを協働したロンドンの設計事務所が「何でもできるんだな」と驚いていたので、「イギリスではできないのか」と聞き返したら、「できない。イギリスの伝統技術は産業革命以降に衰退してしまったから」と言っていました。
日本の伝統技術もいろいろな意味で風前の灯火ではありますが、これだけ多種多様な技術が残っていること自体が世界に類を見ない。フランスやイタリアよりも多いでしょう。この事実を大きく捉えています。冷蔵庫のドアを開けたら材料がいっぱい入っているようなもの。使わない手はありません。しかも、日本の職人はモラルが高く、納期やクオリティを絶対に守ってくれる。
また、僕は伝統技術も、3Dプリンタのような最新の技術も、分け隔てなく捉え、こちらが編集して使えばいいと思っているので、さらにネタが増えます。
― 「ubushina」で最近関わったプロジェクトにはどんなものがありますか?
立川:インテンショナリーズがインテリアデザインを手がけた東京・赤坂の「すし匠 齋藤」のために、和紙を2種類と加賀小紋の布地を誂えました。
― とても素敵です。インテンショナリーズとは東京・目黒のホテル「CLASKA(クラスカ)」でも協働していましたね。
立川:インテンショナリーズを率いる鄭秀和さんとはかれこれ20年近くのお付き合いになります。この「すし匠 齋藤」ではお互いに若い頃はできなかった領域に辿り着いたような感じがありますね。

インテンショナリーズがインテリアデザインを手がけた東京・赤坂の「すし匠 齋藤」。「ubushina」がプロデュースした加賀小紋の布地を座布団カバーに使っている(写真:益永研司)

「すし匠 齋藤」の襖に使われている灰色の和紙は、「ubushina」のプロデュースにより、陶器の釉薬に見立てて伝統工芸士が制作(写真:益永研司)

「すし匠 齋藤」のエントランス。室礼のための収納箱に貼った和紙も「ubushina」のプロデュース(写真:益永研司)
― 立川さんが「伝統技術ディレクター」を名乗るまでの経緯を教えてください。
立川:カッシーナジャパン(当時)の営業職、インテリアのセレクトショップの店長職を経て、1999年に自分の会社を立ち上げました。
店長時代にミラノに行き、アキッレ・カスティリオーニさんやエンツォ・マーリさんといったイタリアデザイン界の巨匠たちに会う機会に恵まれ、「社会や文化を見据え、日本人であることに自覚的になり、君たちの足元にある素晴らしいものを大切にしなさい」と教えられたことが今に至る伏線になっているかもしれません。伝統技術に関わるようになってから、その言葉を日々噛みしめています。言われた当時はあまりわかっていなかったのですが。
伝統技術に関わるようになったきっかけは、独立直後に富山県の高岡市デザイン・工芸センターから商品開発の研究会に呼ばれたことです。
― 高岡は銅器や漆器などの伝統的な技術が息づく地域の代表ですね。
立川:その銅器や漆器の製造技術を用いて新商品を開発するための研究会でした。伝統産業の再生を目指す産官一体のプロジェクトで、プロダクトデザイナーの安次富隆さんがディレクターとして指導にあたり、メーカーや職人、問屋など、異なる立場の人が20人くらい参加していました。そこで伝統工芸の人たちとの接点が生まれたんです。
僕はそれまでの仕事で築いた建築家やデザイナー、小売店とのネットワークを活用できる立場で、東京のインテリアショップで売れそうなものを提案することは難しくありません。実際につくることもできる。けれども商品開発プロジェクトは継続的な事業に発展しなければ意味がなく、継続させるためには流通面を含めて全体の仕組みを設計する必要があります。
デザインによって地場産業を再生させる取り組みはすでに盛んに行われていましたが、そうした仕組みを整えず、そろばん勘定もしなかったから、生き残っているものはほとんどなかった。同じ轍を踏むことだけは避けたいと思いました。
ホテル「クラスカ」で伝統技術の新しい切り口を提示

―展示会を開いて終わり、というプロジェクトがたくさんありました。
立川:考えた末に、「技術を売る」ことを提案しました。商品は樹木にたとえれば果実や花。その手前には幹があり、根っこに続くように、商品は技術という幹があってこそ生まれ、技術の根っこは高岡の場合、400年にも及ぶ。
技術を売るということはつまり、フルオーダーのものづくりに応じる、ということです。高岡の銅器や漆器の製造技術を見て、これは建築家やデザイナー、メーカーの商品開発担当者などが絶対に興味をもつと思いました。需要は確実に集められるし、掘り起こすこともできる。
内装や家具といった、これまでに足を踏み入れたことのない分野からの問いかけは、つくり手に新たな発見や気づきをもたらすはずだ、とも思いました。また、オーダーメイドは在庫を抱えるリスクがありません。
安次富さんと話し合って、この方向でプロジェクトを進めることになり、営業ツールとして、何ができるのかを可視化したサンプルプレートをつくりました。言わば、技術のアーカイブです。


「HiHill」プロジェクトでつくった、漆と金属のサンプルプレートの数々
― それが「HiHill(ハイヒル)」プロジェクトの始まりで、後に「ubushina」事業へと発展するわけですね。高岡だからハイヒルと命名しようというのも立川さんが?
立川:皆、ダジャレが好きで(笑)。気づいたら、飲み会の席で決まっていました。
漆や金属の職人たちとサンプルプレートをつくるのはおもしろかった。まっさらなプレートを手にした職人は、いつもやっている技術をまず施します。プレートはたくさんあり、なかなか減らない。すると、親父のときはどうしていたか、じいさんのときは、自分ならどうする、と考え始める。あるいは僕らが、そのテクスチャーのほうがきれいですよ、と言って作業の途中でストップをかける。そうやって半年がかりで約180種を用意しました。並べたときは壮観でしたね。
サンプルを持って設計事務所を回ると、反応は上々。ところが、その先の段階でつまずきました。
― 何があったのですか?
立川:職人はそれまで、産地の問屋としかやりとりしたことがなく、設計事務所の意向を汲むことに慣れていません。この技術を使ってテーブルをつくりたいという話をもらっても、納品まで1年かかりますというような訳のわからない見積書を出してきて、まるでコントでした。高岡市デザイン・工芸センターの人たちが、そこを懸命に調整してくれたのは本当に救いでしたが、しばらく鳴かず飛ばず。
そんなところに「クラスカ」の企画が持ち上がりました。2002年のことです。

「CLASKA」の2003年オープン当時の様子。改修設計はインテンショナリーズが手がけた。カウンター側面は「布張り漆塗り」の技術を用いている(写真:Nacasa & Partners)
― 「クラスカ」の「再生」というコンセプトは時代を先取りするもので、老朽化した建物に新たな価値を与えるリノベーションの走りでした。
立川:僕はプロジェクトチームの一員として家具や什器の製作管理を担当し、「再生」のコンセプトにもう一つ、「伝統技術の再生」というテーマもインストールしました。現代に通じる価値を見失って迷走する伝統技術にも、新しい切り口が必要だと。
「クラスカ」では内装や家具、照明器具に、漆や鋳物、竹編み、ブナコなどを用い、伝統技術の先進的なアウトプット例として大いに話題になりました。また、僕にとっては建物内がすべてショールームみたいなものだから営業がはかどり、「技術を売る」仕事をようやく軌道に乗せることができました。


「CLASKA」のロビーなどに採用された真鍮鋳物のスタンドライト。同じ型を流用してペンダントやブラケットも製作。着色せず、生地のままなのは、高度な技術があるからこそ可能だった(左の写真:Nacasa & Partners 右の写真:梶原敏英)
「CLASKA」のロビーなどに採用された真鍮鋳物のスタンドライト。同じ型を流用してペンダントやブラケットも製作。着色せず、生地のままなのは、高度な技術があるからこそ可能だった(上の写真:Nacasa & Partners 下の写真:梶原敏英)
― 「クラスカ」は2003年のオープンから15年近く経ちますが、インテリアに見られる伝統技術のあれこれは全く古さを感じさせません。
立川:きちんとした本物の素材を使っているから。このひと言に尽きます。それに伝統技術はもともとサステナブルなもの。さもありなん、というところです。
(TALK #12に続く)
バックナンバーを見る

TALK #20
素材にひそむ力の強さを拠り所にして

TALK #19
その場所らしさをデザインや素材で表現する

TALK #18
温故知新を大切にした空間づくり

TALK #17
理想の空間を具現化する

TALK #16
壁紙が持つ空間の支配力はすごい。

TALK #15
遠くから見ても。近くで見ても、面白い。

TALK #14
驚きや喜びのあるホテル空間をつくる

TALK #13
ホテル空間の新しい表現に挑む

TALK #12
日本の伝統技術で高付加価値を目指す

TALK #11
日本の伝統的な素材や技術をインテリアに

TALK #10
部屋がオーケストラなら、壁面は指揮者

TALK #09
インテリアを豊かにする素材の使い方

TALK #08
風合いを感じさせる素材の使い方がある

TALK #07
素材の風合いを常に意識して

TALK #06
デザインはコミュニケーションの方法

TALK #05
空間の密度を保つ素材の選び方

TALK #04
プロジェクトの完成度を高める素材の力

TALK #03
素材のポテンシャルを引き出し、現象を起こす
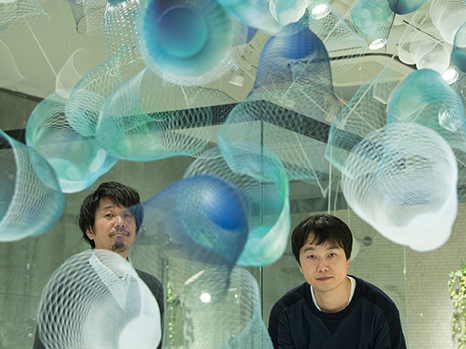
TALK #02
視点を変えると、素材の使い方がぐんと広がる
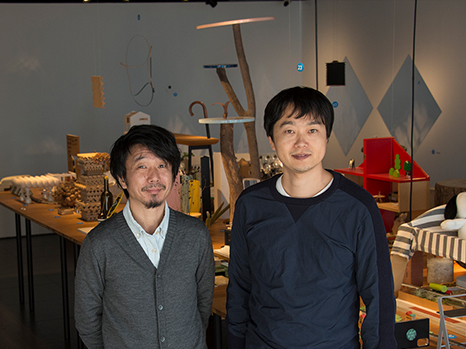
TALK #01
一つの「敷地」で、主役となる素材を決める


