遮光カーテンの選び方|通常のカーテンとの違いや部屋別のおすすめ等級
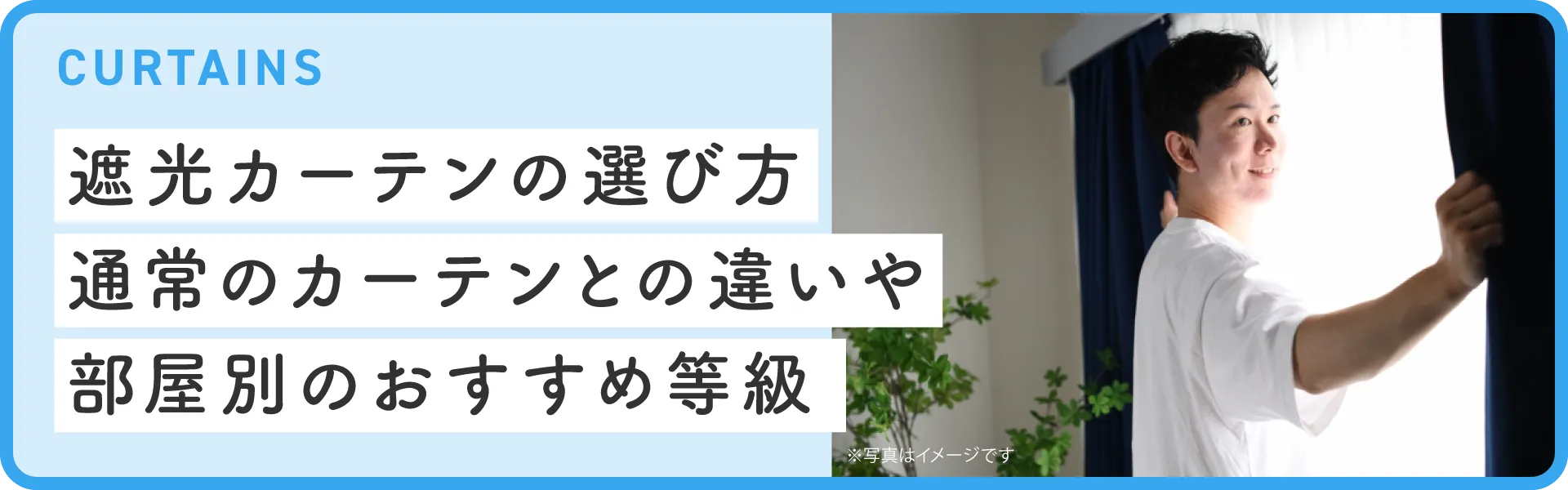
カーテンはお部屋のアクセントになるほか、屋外からの視線を遮ったり、冷暖房の効率を向上させたりするなど幅広い役割を担っています。中でも、カーテンの機能として遮光性を求めている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、遮光カーテンと通常のカーテンとの違いや、遮光カーテンを取り入れるメリット、等級ごとの遮光率の違いについてわかりやすく解説しています。遮光カーテンのトレンドや選び方のコツもあわせて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
遮光カーテンとは

品番:AC2398
はじめに、遮光カーテンは通常のカーテンとどう違うのか、具体的な特徴を確認しておきましょう。遮光カーテンを取り入れるメリットや等級の見方を知っておくことが大切です。
光を通しにくいカーテン
遮光カーテンとは、通常のカーテンと比べて光を通しにくいカーテンのことです。通常のカーテンにも光を和らげる効果はありますが、この機能をさらに強化したものが遮光カーテンと考えてください。
光を遮る効果が高いということは、屋外からの光を通しにくくなると同時に、室内の光が漏れにくいカーテンともいえます。カーテンにはお部屋のアクセントとしての効果をはじめ、プライバシー保護や遮熱などさまざまな機能があります。その中でも、とくに光を遮る効果が重視されているのが遮光カーテンです。
遮光カーテンを取り入れるメリット
遮光カーテンをお部屋に取り入れることで、さまざまな効果が期待できます。
- ・安眠効果:日光や街灯など窓外からの光を遮り、睡眠の質を高める
- ・プライバシー保護:室内光の漏れを抑え、屋外から部屋の様子を見えにくくする
- ・遮熱/断熱効果:部屋に差し込む日光を抑え、室内に入る熱を遮る
- ・日焼け防止効果:床や壁、家具などが日焼けによって劣化するのを防ぐ
遮光カーテンの等級
遮光カーテンには1等級から3等級の3段階の遮光等級が設けられています。等級ごとの遮光率は次のとおりです。
- ・3等級:遮光率99.4以上99.8%未満(光がほどよく取り込まれる)
- ・2等級:遮光率99.8以上99.99%未満(強い西日なども通しにくい)
- ・1等級:遮光率99.99%以上(完全に閉めると室内がほぼ真っ暗になる)
このように遮光カーテンと一口にいっても、等級ごとに遮光率が異なります。カーテンを設置するお部屋の用途や過ごし方に応じて、どの程度まで遮光したいのかを考慮することが大切です。
遮光カーテンのトレンド
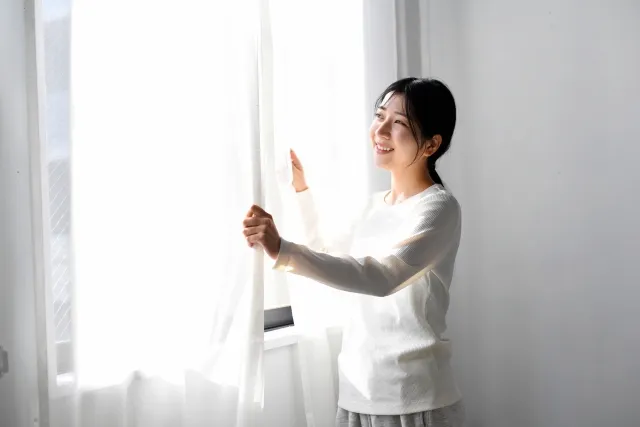
※写真はイメージです。
近年の遮光カーテンのトレンドを紹介します。多くの方に選ばれる傾向があるのは「明るい色の遮光カーテン」や「機能性に優れたカーテン」です。
1. 明るい色の遮光カーテン
遮光カーテンと聞くと、暗い色のカーテンをイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際には暗い色だけでなく、通常のカーテンと同じような明るい色のカーテンも数多くあります。カーテン自体が明るい色であっても、遮光効果が低いわけではありません。
明るい色の生地でも遮光性を確保できるのは、生地が厚めに織られていたり、生地の表面から見えないように黒糸が織り込まれていたりするからです。暗い色のカーテンは重厚な印象をもたらす効果が期待できますが、重厚さよりも華やかさや軽やかさを求める方は明るい色の遮光カーテンを選ぶとよいでしょう。
【明るい色の遮光カーテンの例】

品番:AC2032
アイボリー系の明るい色調でありながら、遮光率2級の機能を備えています。再生糸を使用したマットな質感で、ナチュラルなインテリアにおすすめです。やわらかくヒダがきれいに仕上がる点も特長です。

品番:AC2462
グリーンの無地カーテンです。鮮やかなカラーでありながら、遮光1級性能を備えています。お部屋のアクセントとして取り入れていただけるカーテンです。
2. 機能性に優れたカーテン
遮光カーテンの中には、遮光効果以外にもさまざまな機能を備えているものがあります。たとえばウォッシャブル対応のカーテンならご家庭で洗濯ができるため、手軽にお手入れができる点がメリットです。また、遮熱機能や防炎機能が備わっている遮光カーテンもあります。窓から入りこむ熱気や冷気の影響が気になる方や、火災発生時の安全性を重視したい方は、こうした機能を兼ね備えた遮光カーテンを選ぶとよいでしょう。
【機能性に優れたカーテンの例】

品番:AC2442
ざっくりとした織で、マットな質感と光沢感の対比が美しいカーテンです。遮光2等級でありつつ、ウォッシャブル対応のため、ご家庭で手軽にお手入れができます。

品番:AC2417
タテ糸とヨコ糸にそれぞれ異なる色の糸を使って織られた、独特な質感のあるカーテンです。遮光2級+防炎機能を備えており、ご家庭での洗濯にも対応しています。
遮光カーテンを選ぶコツ
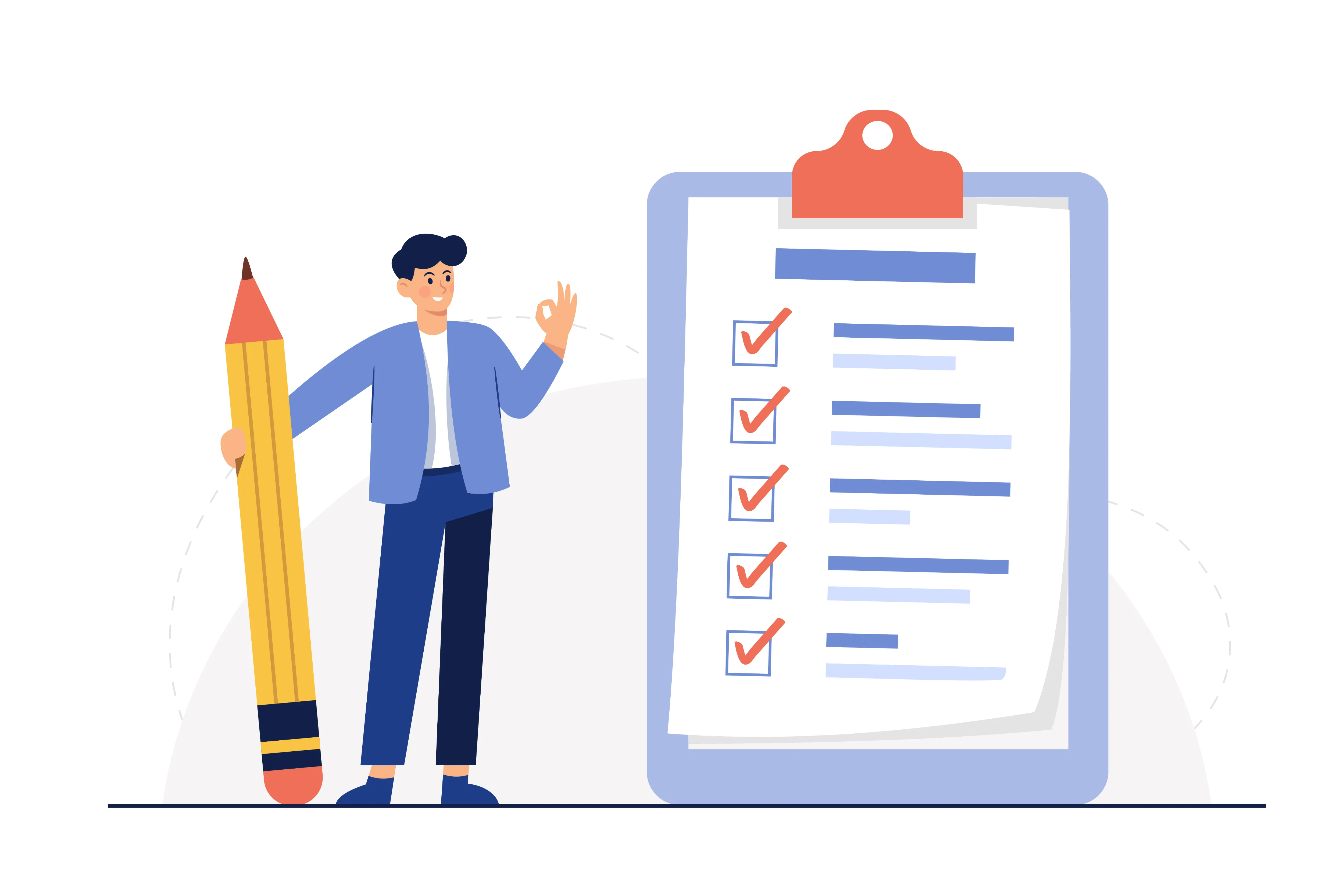
※イラストはイメージです。
遮光カーテンを選ぶ際のコツを紹介します。カーテン選びで失敗しやすいポイントでもあるため、次の5点を意識して選ぶことが大切です。
1. 求める機能に応じて選ぶ
カーテンの遮光等級は、求める機能に応じて選びましょう。遮光効果をどの程度求めるのかによって、適切な遮光等級は異なります。たとえば、屋外から差し込む光を適度に抑えたい場合は3等級、プライバシー保護を重視したい場合は2等級といったように、目的に合った遮光等級を見極めるのがポイントです。
2. お部屋全体のバランスを考慮する
遮光カーテンの色や柄、生地感を選ぶ際には、カーテンを単独で選ぶのではなく、お部屋全体のバランスを考慮することが大切です。床や壁紙の色との対比や、家具などの色とのバランスを考えておくと、統一感のあるコーディネートを実現しやすくなります。
カーテンは大きな面積を占めるインテリアのため、お部屋全体のイメージを左右するケースが少なくありません。機能性だけでなく、デザイン面も重視して選ぶことをおすすめします。
3. 遮光効果が高いほど良いとは限らない
遮光カーテンを取り入れるからには遮光効果が高いものを選びたい、と考えがちですが、遮光効果は高ければ高いほど良いとは限りません。お部屋での主な過ごし方を想定し、用途に合った遮光効果のものを選ぶことが重要です。
たとえば、寝室に遮光カーテンを取り入れる場合、遮光効果が高すぎることが原因で寝過ごしやすくなる、といったことにもなりかねません。一般的には遮光効果が高いカーテンほど価格も高くなる傾向にありますが、価格が高い=より適切な効果を得られる、とは限らない点に注意しましょう。
4. 遮光性と遮熱性は分けて考える
遮光性が高いカーテンは遮熱性にも優れていると思われがちですが、必ずしもそうではありません。遮光カーテンは光を通しにくいカーテンであるのに対して、遮熱カーテンは日光による熱を反射・吸収することで温度上昇を抑える役割を果たします。重視する機能がそれぞれ大きく異なることから、遮光効果が高いカーテンには遮熱性も期待できるとは言い切れないのが実情です。遮光性とあわせて遮熱性も重視したい場合は、遮熱効果が高いカーテンを選ぶ必要があります。このように、遮光性と遮熱性は分けて考えるのがポイントです。
5. 必ずサンプル生地を取り寄せて検討する
遮光カーテンを選ぶ際には、通常のカーテンと同様に必ずサンプル生地を取り寄せて検討することをおすすめします。カタログなどに掲載されている写真の色と、実物の色がやや異なることもめずらしくないからです。また、生地の質感や手ざわり、光沢の具合などは生地の現物を見ないと判断できない面があります。
実物のカーテン生地を確認するには、サンプル生地を取り寄せるほか、ショールームで実物を見ておくのもおすすめの方法です。写真だけで判断せず、実物を見て比較検討することが大切です。
機能性やトレンドへの理解を深めて遮光カーテンを選ぼう
遮光カーテンは通常のカーテンと比べて光を通しにくいため、安眠効果やプライバシー保護などの効果が期待できます。遮光等級ごとの違いを押さえつつ、その他の機能やトレンドへの理解を深めて、お部屋の用途やイメージに合ったカーテンを選びましょう。
お部屋全体のコーディネートをよりイメージしやすくするには、ショールームや販売店でカーテンの実物をご覧になることをおすすめします。また、手軽にコーディネートを試したい方には、着せ替えシミュレーションサイトの活用もおすすめです。サンゲツでは、カーテンをはじめ床や壁紙などの色を自由に組み合わせられる「Myコーデ®」を提供しています。お気に入りのコーディネートをダウンロードしたり、URLをハウスメーカーや工務店と共有したりすることも可能です。マイコーデ®を活用して、イメージに合った遮光カーテン選びを実現してみてはいかがでしょうか。



